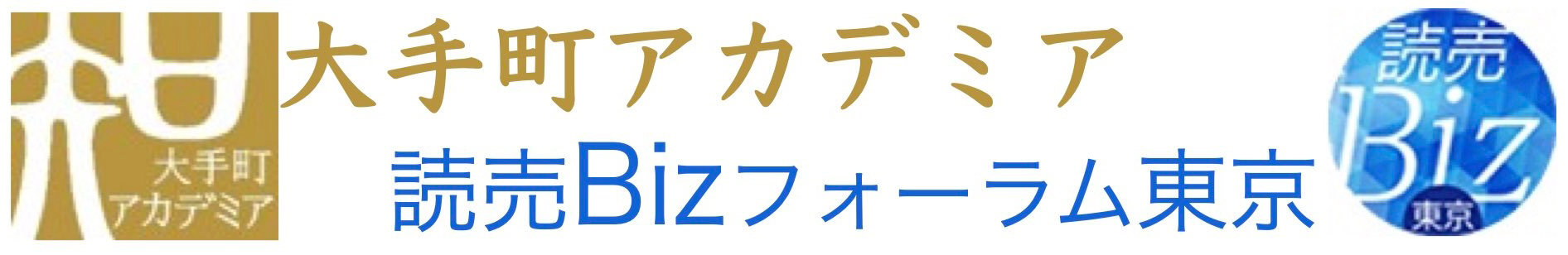 オンラインセミナー
オンラインセミナー
:講演要旨
激変する世界と監査の将来~不正と対峙する公認会計士
川端 千暁 氏中央大学商学部 助教
高橋 徹 読売新聞東京本社 調査研究本部主任研究員
-
中央大学×大手町アカデミア「激変する世界と監査の将来~不正と対峙する公認会計士」が6月17日にオンラインで開催されました。
中央大学商学部助教の川端千暁氏が講演で、企業の経営者・従業員の不正や問題ある行動をチェックする「情報保証機能」と、企業が提示する財務諸表について公認会計士が調べ、投資に有用な情報を保証する「モニタリング機能」という監査の二つの経済的な機能が昔からある、と解説しました。
1602年に最初の株式会社であるオランダ東インド会社が設立された「大航海時代」からの歴史も振り返りながら、「バブル経済」の語源ともなった1720年、英国で起きた「南海泡沫会社事件」や、2001年、米国でエネルギー会社が粉飾により破綻した「エンロン事件」などを紹介。その後も続く近年の会計不正と監査規制の改革を経て、二つの機能も変化している、と指摘しました。情報保証機能では「財務報告・サステナビリティー情報など多様な情報の保証・ガバナンス」、モニタリング機能では「スタートアップ企業のための効率的なガバナンス体制の構築」という二つの軸の変化が2010年代から起きている、と分析しました。
川端氏は、会計士を目指す大学生や高校生に向け、「監査・ガバナンスのスペシャリスト」と「会計・ビジネスのゼネラリスト」という二つの進路を示し、「試験勉強も大事だが、深い教養と最新の色んな知識が必要なので、それを身につけられる中央大学に進学して、どちらかの道に進んでほしい」と期待を込めました。
続いてのトークセッションでは、「激変する監査の機能」「公認会計士の現状と未来」「スタートアップと会計専門職の変化」の三つのトピックで議論が展開されました。視聴者からも「報酬をもらいながら監査すると、利益が相反するように感じるが、どのように意識のバランスをとっているのか」「AIが進化する中、会計を学ぶ大学生や高校生に どのような資質がこれからの監査に求められるのか」など、多くの質問が寄せられました。
講師プロフィール
-
川端 千暁 氏 中央大学商学部 助教
中央大学商学部、助教。財務諸表監査やコーポレートガバナンスに関する研究を専門としています。関西学院大学で商学と法学を学び、博士(商学)号を取得。主に、法的責任や監査市場が監査人の行動に与える影響(監査人のインセンティブ)に興味があります。監査やガバナンスを研究テーマとして多様な方法や切り口でアプローチしています。
好きなことは、不正や粉飾の事例の調査と学生指導。一児の父。
Xアカウント:@ac2_kwbt
-
高橋 徹 読売新聞東京本社 調査研究本部主任研究員
1990 年読売新聞社入社。千葉支局を経て経済部で財務省、日本銀行、金融庁、総務省、国土交通省、流通・商社など、政治部で民主党を担当。経済部次長、静岡支局長、調査研究本部主任研究員、同管理部長、北海道支社次長を経て、2024年6月より現職。25年2月に中央大学×大手町アカデミア第9回「経済学で学ぶ課題解決へのヒント~暮らしやすい地域のしくみづくり」の聞き手を務めた。日本証券アナリスト協会認定アナリスト(CMA)。