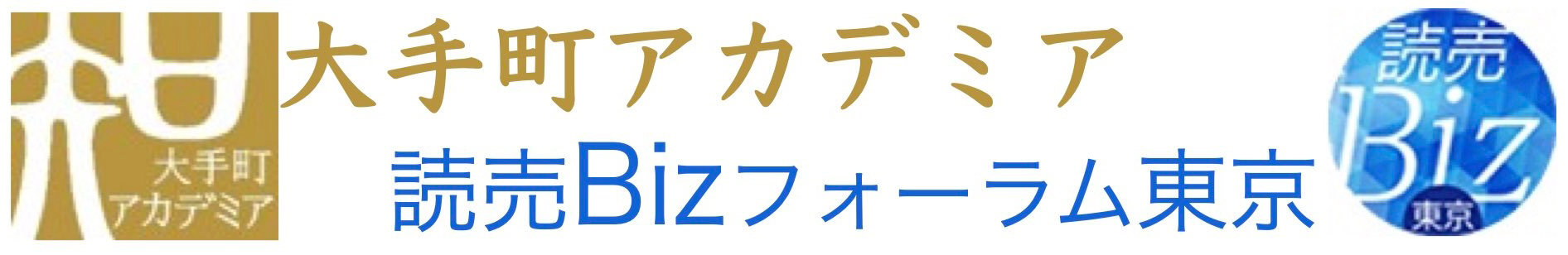 オンラインセミナー
オンラインセミナー
:講演要旨
江戸時代の本棚~蔵書が語る知の形成・共有・継承
工藤航平 氏国立歴史民俗博物館研究部 准教授
植田 滋 読売新聞東京本社調査研究本部 研究員
-
大手町アカデミア×人間文化研究機構「江戸時代の本棚~蔵書が語る知の形成・共有・継承」が10月8日にオンラインで開催されました。
国立歴史民俗博物館 研究部の工藤 航平 准教授が 、 残された蔵書目録を手掛かりに 近世の知のありようを探る「蔵書研究」について、研究の現在地と、江戸時代の蔵書を研究する意義について概説しました。続いて 具体的な研究事例として、加藩で十村役を務めた喜多家や、西袋村(現在の埼玉県八潮市)で名主を務めた小澤豊功の 蔵書目録から見える、地方の個人の知の形成 整理と変容 について 解説しました。
講演後には、工藤准教授と読売新聞東京本社 調査研究本部の植田 滋 研究員とのトークセッションが行われました。トークセッションでは 「蔵書から見る江戸時代の知の世界」「現代の蔵書」「蔵書研究の魅力」などの話題を展開しました。
Q&Aでは「個人の 蔵書が 世代交代等により 廃棄や 散逸の 危機にありながら 地域社会で どのように 継承されてきたのでしょうか?」
「庶民と 武士階級など 身分によって 蔵書の 内容や 利用目的に 違いがあったのでしょうか?」など 熱心な質問が寄せられました。
講師プロフィール
-
工藤航平 氏 国立歴史民俗博物館研究部 准教授
総合研究大学院大学博士後期課程修了、博士(文学)。日本近世・近代史、アーカイブズ学を専門とする。国文学研究資料館研究部機関研究員、東京都公文書館専門員を経て、現職。主要な研究テーマは、近世社会における知識の多様性とその構築・継承プロセスの解明、知識の形成・共有・継承と地域社会の変容である。主要業績に、『近世蔵書文化論-地域〈知〉の形成と社会』(勉誠出版、2017年)、「日本近世社会における知識形成と蔵書文化」(『歴史学研究』第1031号、2023年1月)など。
-
植田 滋 読売新聞東京本社調査研究本部 研究員
1965年、東京生まれ。1990年入社、前橋支局などを経て、1999年から20年以上、東京本社文化部に在籍した。主に論壇・宗教を担当し、2008年から6年間、読売新聞文化面の論壇時評「思潮」欄を執筆。論説委員(文化・スポーツ担当)、文化部長も歴任した。